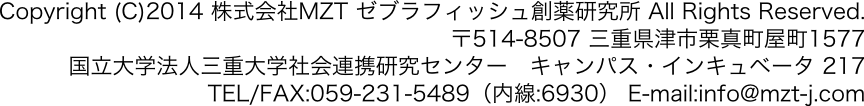最近の記事
- 2025/12/10
- 2026年1月21日(水)13:00-16:30PDXZネットセミナー
- 2025/12/04
- AIDXプレシジョン患者がん移植システムによるゼブラフィッシュ創薬と個別化医療
- 2025/12/02
- AIプレシジョン患者がん移植ゼブラフィッシュシステム(PDXZ)
- 2025/10/16
- AIDXプレシジョン患者がん移植システムによるゼブラフィッシュ創薬と個別化医療
- 2025/06/17
- 患者がん移植ゼブラフィッシュモデル(PDXZ)の臨床展開
- 2025/06/02
- ポドサイトパチー創薬スクリーニング
| 2020/04/10 |
薬理スキル基本DMSO
薬理スキルDMSO
阻害剤調製時に知っておきたい5つのポイント
2019年4月24日
間違った扱い方が阻害剤の効果を激減させる
生物の体内でさまざまな働きを担っている生理活性物。その一部は阻害剤として利用でき、生命の仕組みや体内分子の機能を調べるツールとして非常に有用です。ただし、生理活性物質は扱い方を誤ると活性が減少したり失われたりしてしまいます。
活性が失われた阻害剤を使って実験を行うと、何が原因で阻害されないのか区別ができず、正しい結果にたどり着くまで時間がかかってしまいます。また、用いた阻害剤が理論通りの効果を発揮しなかった場合は、実験結果を誤って解釈してしまいます。
この記事では、阻害剤の扱い方について留意すべきポイントを紹介します。以下の5点を見直し、実験の精度を高めていきましょう。
1. 有機化合物系阻害剤を水で溶解してはいけない
生理活性をもつほとんどの有機化合物は、水に溶解させるとただちに活性を失います。製品データシートを確認して適切な溶媒を選びましょう。
有機化合物系阻害剤は一般的にジメチルスルホキシド(dimethylsulfoxide:以下、DMSO)に溶解させれば、溶液として保存可能です。ただし、DMSOの中に水が含まれていると阻害剤の活性に影響を及ぼしてしまいます。DMSOの保管は湿気を避け、容器を密閉して冷暗所に。最適な方法は、湿気を吸収していない新しいDMSOボトルを開封してすぐに使用することです。阻害剤の溶媒に用いる場合は、なるべく小容量の製品を購入するとよいでしょう。
2. 有機化合物系阻害剤は水系バッファーを用いて希釈してはいけない
DMSOに溶かした有機化合物系阻害剤は、実験に使う直前に希釈して最適な濃度に調製します。このとき溶媒に水系バッファーを用いると、阻害剤が沈殿する場合があります。特に水溶性が低い細胞培養培地では、最終濃度より濃い濃度で水系バッファーを使って希釈すると、沈殿や凝集が生じてしまいます。
このような事態を防ぐためには、DMSOを用いて希釈系列を調製するとよいでしょう。実験の際には、その希釈系列から分取したサンプルをバッファーあるいは培地と混合して最終濃度に調製します。ただし、ストック溶液をDMSOで希釈するときは、使用するDMSOの量に注意し、DMSOの最終濃度が細胞毒性を与えないことを確認しましょう。一般的に細胞培養系に添加しても影響がないDMSO濃度は、0.1%(v/v)以下と言われています。また、実験の際は、DMSOを単独で添加するネガティブコントロールも取る必要があります。
3. ペプチド系阻害剤は-20℃で保管する
ほとんどのペプチドは凍結乾燥状態で-20℃で保管すれば、数年間安定です。実験に使うときは、直前にデシケーター中でバイアルの温度を室温に戻しましょう。ペプチド中のシステイン、メチオニンならびにトリプトファン残基は、酸化を防ぐために特別な準備が必要な場合もあります。
溶媒には、蒸留水や濃度調製済みの酢酸など除湿状態で保存された適切な溶媒を選択します。調製したペプチドストック溶液は必要量ごとに分注し、pH 5〜7を保ちながら-20℃で保管してください。多くのペプチドは溶媒に溶解した時点で徐々に分解が始まるので、長期保存はおすすめできません。また、ペプチドストック溶液をバッファーや生理食塩水に添加する場合は、ペプチドが完全に溶解してから実験を実施してください。溶媒に完全に溶けない場合は、超音波処理(ソニケーション)を行いましょう。
4. ペプチド濃度の測定にはIR法がおすすめ
一般的なペプチド濃度測定法は、凍結乾燥粉末の重量測定、紫外線の吸光分析、アミノ酸分析です。しかし、凍結乾燥粉末の重量測定は正確に行うのはなかなか困難です。というのも、測定対象の粉末はその10〜70%が結合水あるいはペプチドが塩になるための対イオンだからです。
紫外線の吸光分析は波長280 nmの光線の吸光度から濃度を推定する方法ですが、これはアミノ酸配列にトリプトファン残基とチロシン残基を含まなければ適用できません。波長205 nmの光線の吸光度が測定可能な場合は、アミノ酸組成によらず正確な濃度推定が可能ですが、同時にこの波長は多くの化合物や溶媒にも吸収されるため、注意が必要です。
アミノ酸分析はペプチド分析において最も正確な手法である一方、特別な測定装置を必要とし、時間も費用もかかるという短所があります。
おすすめは、簡便かつ比較的正確な手法である赤外分光法(infrared spectroscopy:以下、IR法)です。IR法は、ペプチド結合 [-(C=O)-NH-] 中のC=O二重結合とC-N単結合が示す赤外線の吸収からペプチド濃度を測定する方法。実施には、アミノ酸残基の重量分布をカバーできる適切な標準サンプルを用いた検量線が必要です。また、水分子が赤外線を吸収する性質があるため、水分を含まない測定サンプルを用意しましょう。
5. 精確な分子濃度を求めるには吸光光度法で測定しよう
吸光光度法は、既知の溶媒に溶けた分子の濃度や純度を正しく測定しなければならない場合に便利です。以下のような条件にあてはまるときは、吸光光度分析による物質濃度測定を行いましょう。
• 実験に使用する化合物が特定波長に特徴的な吸光スペクトルを示す場合
• 物質の力価あるいは純度を、事前に測定しておかなければならない場合
• 分子の濃度を精確に調製しなければならない場合
吸光度と分子濃度の関係式はランベルト・ベールの法則によって与えられます。
A=abc(式1)
ここで、A:吸光度、a:吸光係数、b:光路幅[cm]、c:特定波長で吸光を示す分子の濃度です。光路幅bが1 cm、分子濃度cが[mol/L]のとき、aはモル吸光係数εに置き換えて記載できます。モル吸光係数εは、特定分子1 molが特定波長に対してある定まった条件下(溶媒、温度、pH)で示す定数[L/mol]です。εは分子種の同定や純度測定にも用いることが可能です。
例として、ビリルビンの純度測定を紹介します。ビリルビン(分子量584)のεは25℃のクロロホルム中で60,700です。純度100%のビリルビン5 mg/L(0.005 g/L)が光路幅1 cmのキュベット中で示す吸光度は(式1)に基づくと次式のとおりです。
A=60,700×1×(0.005/584)=0.520(式2)
したがって、もしクロロホルムで調製したビリルビンの吸光度が25℃において0.49だった場合、その純度は約94%(0.49/0.52×100)になります。
生化学分野あるいは毒性研究において、[g/dL]での濃度表記は、[mol/L]表記よりもよく見られるため、[g/dL]単位の定数が用いられることがあります。また、これらの分野では分子量が正確に知られていない分子を扱わねばならないこともあります。たとえば、光路幅bが1 cm、分子濃度cが1 g/dL(1%)のとき、吸光度はA 1% 1cm(単位の正式表記は1%の下に1cmを配列)と記載されます。この値は定数値であり、吸光係数と同義です。
吸光度と濃度の直接的な相関は、特定の装置と定められた実験条件のもとで実測値として定めます。吸光度は、ある上限濃度までは濃度と直線的な相関を示します。そのため、特定の条件範囲において、濃度cは吸光度Aとその補正係数によって推定可能です。
c=A/ab
実験条件が一定(a≠0かつb≠0)であれば、吸光係数aと光路幅bは一定なので、1/abをKと置くことが可能です。よって、以下のように記述できます。
c=A/ab =AK(式3)
Kを求めるためには、濃度cが既知の標準サンプルが必要です。濃度cは吸光度測定によってK=A/cの関係式から算出可能です。
(式1)は分光測定による物質の濃度と吸光度の基本関係式です。この式を応用することで、吸光度の測定による分子の純度測定(式2)や物質の濃度推定(式3)を行うことができます。ぜひ、みなさんの研究にも役立ててくださいね。
以上、阻害剤調製時に知っておきたい5つのポイントを解説しました。阻害剤に限らず、化合物を実験に使用する際には、物質に対する正しい物理化学的な理解が必要です。実験を正確に行い研究の効率を向上させるために、基礎をしっかり押さえておきましょう。